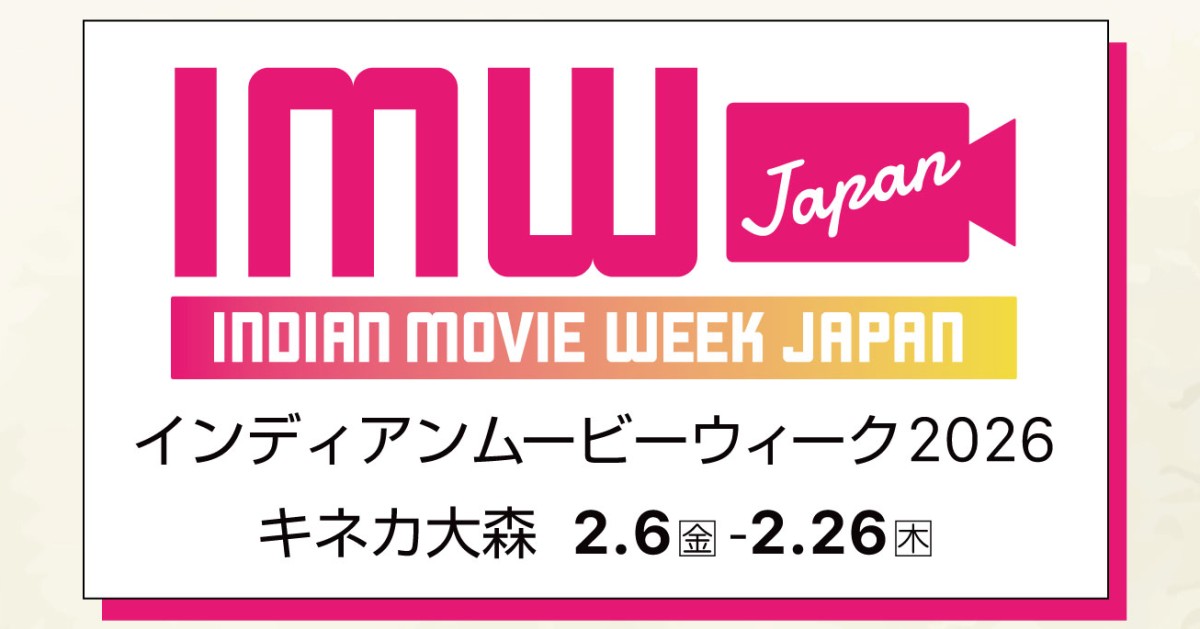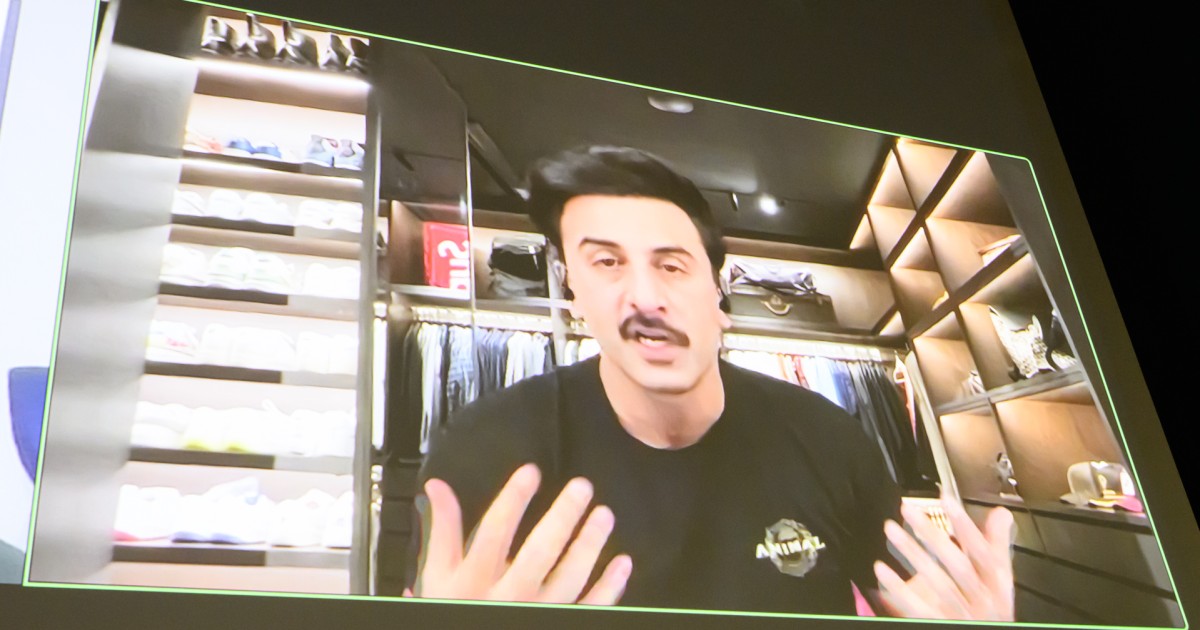映画『ツーリストファミリー』レビュー|移民家族がもたらす ”おかしみ” と ”繋がり”
真っ暗な夜の海岸。荷物を手にして海に向かう何人かのシルエットが徐々に見えてくる。スリランカ北部のヴァルヴェッティトライから、インド南部にあるラーメーシュワラムを目指して漕ぎ出すひとつの家族。母国の惨状から逃れた彼らは、チェンナイという新しい土地で暮らしをスタートさせることはできるのか。浜辺にたどり着いた一家の前に早速最初の試練が立ちはだかるーー。
※作品の内容に一部触れている内容となっております。予めご了承の上、ご覧ください。
物語の下敷きにあるスリランカの社会事情
弱冠25歳の新人監督アビシャン・ジーヴィントによる小規模作品が、スーパースターのラジニカーントや、『RRR』(2021)や『バーフバリ』シリーズ(2015/17)でお馴染みのS・S・ラージャマウリ監督、人気俳優・プロデューサーのナーニといった映画業界の重要人物たちから絶賛され、2025年にインド国内でタミル語圏を中心に大ヒット。インド映画としては短めの127分で描かれる心温まる人情喜劇で、肩肘張らず笑って泣いて楽しめる映画ではあるのだが、家族がインドにやってきた理由はこの数年で現実に起きたスリランカの情勢が下敷きになっている。作中では深く語られないスリランカのこの数年の状況、社会的な背景を知っておいた方が物語を飲み込みやすくなるはずなので、まずはそこからスタートしたい。
父のダース、母のワサンティ、2人の息子たちニドゥとムッリの4人が密航するという大きな決断をしたのは、スリランカの経済破綻からくる生活の困窮が理由だ。北海道より少し小さいくらいの国土に2200万人が住むスリランカでは、複雑な民族問題を発端とした内戦が26年間続き2009年に終結。その後は政権交代を経て経済再建をしてきたのだが、財政面が脆弱で2022年には外貨不足での輸入が困難に、新型コロナのパンデミック以降観光収入が落ち込み、さらにロシアによるウクライナ侵攻で世界的な物価の上昇も重なったことによって、1948年イギリスからの独立以来、最悪の経済危機に陥った。輸入品が入ってこないので、食料品の価格が急騰。発電に必要なエネルギー燃料を調達する外貨が不足し輸入することができないため、電気も車も満足に使えない。病院では医薬品が不足、学校で使う紙やインクもなく、新聞も発行できない…など市民生活のすべてに国家の財政難が重くのしかかった。こうした状況を招いた大統領の辞任を要求する市民のデモ隊が大統領公邸に突入した映像は、日本でも報じられていた。
そんな背景から苦労して海を渡った一家だが、劇中では基本的に明るく穏やかであまり悲哀を感じさせない。物語の軸にあるのはあくまでもスリランカからやってきた家族とチェンナイで出会ったご近所さんたちとの交流で、どんな人でも観やすいように間口を広げるキャラクター造形になっている。その中でも特に次男ムッリ(演じるのはインド公開当時9歳のカマレーシュ・ジャガン)の頭の回転の速さ、利発な物言いについ感心して笑ってしまう。彼が思いついた悪知恵が一家の明暗を左右する展開も、脚本の巧さと俳優の芝居の個性が有機的に結びついていて好感をもった。

© Million Dollar Studios C MRP Entertainment.
カルチャーギャップが生む ”おかしみ”
さて、もうひとつ鑑賞前に押さえておくとより理解が深まるポイントになるのが本作の中の言語の使い分けだ。警察や近所の住人に素性を悟られないように必死にインド人のふりをする主人公の一家は、スリランカ北部のスリランカ・タミルコミュニティーで使われるタミル語の話者である。彼らがたどり着いたチェンナイで使用されるタミル語とは異なっており、インドに住むタミル人には理解が難しいそうだ。疑われまいと気を張ってチェンナイ・タミルで話そうとする父のダースもうまくスイッチできず、スリランカのタミル語が出てしまう。劇中の日本語字幕では、かなりかしこまった古めかしいイメージの翻訳でその違いが表現されている。タミル語とひとくちに言っても地域によってもカーストによっても方言がある。その言語のズレによって家族がどこからやってきたのか気づく住民と、バレないようにと平静を装う家族のギャップがおかしい。その背景にはインドにおけるスリランカ・タミルの法的地位が不安定であるという人権の問題も隠れているのだが、少しの緊張感を携えたユーモラスなシーンとして描かれる。会話のやりとりで、カーストや出身地の違いによって生じる市井の人々の生活のレイヤーをさりげなく伝える手腕が見事だ。

© Million Dollar Studios C MRP Entertainment.
南インドの映画というと、つい力強い歴史大作や派手なアクションを思い浮かべるが、多民族、多言語、多宗教の国インドで本作が広く受け入れられたのは、多文化が混ざり合ったことによるカルチャーギャップを「摩擦」としてではなく違いから発生する「おかしみ」として描いたからではないかと想像する。特に前述した言語の部分は、多くの人が共感できる“あるある”なのだろう。それに加えて、スリランカからやってきた家族の人の良さ、純朴さが自然なかたちで住民たちを繋いでいくさまは、経済成長する大国でお金や権力がないと他者から慕われないという考え方が強固になる中、別の価値観にシンパシーを感じる人々を惹きつけたはずだ。これまでの映画では強く威厳のある男性として描かれがちだった父親像を、きちんと過ちを認め反省するひとりの人間として心の柔らかい部分を描いたことにも変化を感じた。
これまで日本で公開されてきたコメディの枠組みで社会問題を扱ったインド映画のヒット作として、2013年に日本でも公開した『きっと、うまくいく』(2009)や、伝記映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』(2018)が記憶に刻まれているが、コメディ以外の近年公開された作品ではカンヌ国際映画祭でインド映画史上初のグランプリを受賞した『私たちが光と想うすべて』(2024)や、ケーララ州北部の上位カーストの家庭に根深く残る家父長制を描き支持を得た『グレート・インディアン・キッチン』(2021)など舞台になる土地もテーマも多様化し、日本の観客にとってインド映画のイメージが拡張されつつある。
文化も言語も違う他者にはどんなバックグラウンドがあるのか。どんな苦労があってここにたどり着いたのか。想像力をもち、コミュニケーションを試みて知ろうとすることでしか軋轢は解消しないのだ。この映画はあたたかく軽妙な筆致で、遠くて近い隣人との付き合い方のヒントを教えてくれる。

© Million Dollar Studios C MRP Entertainment.
キャストほか
監督・脚本:アビシャン・ジーヴィント
出演:シャシクマール、シムラン、ミドゥン・ジェイ・シャンカル、カマレーシュ・ジャガン、ヨーギ・バーブ
2025年 / インド / 127分 / タミル語 / シネマスコープ / カラー / 5.1ch
原題:Tourist Family / 配給:SPACEBOX
場面写真






すでに登録済みの方は こちら