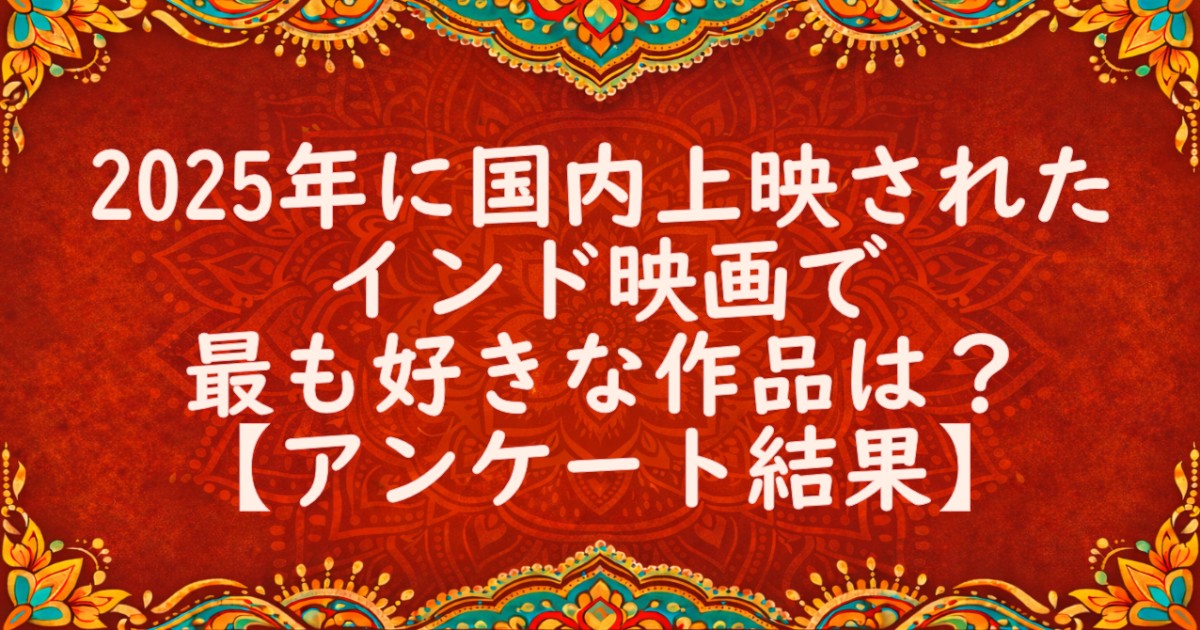『マライコッタイ・ヴァーリバン』は、土の香りと清澄な空気の中での“映画的な禅”
本記事ではネタバレに配慮し、作品の魅力を中心にお届けしていますが、 内容に触れる箇所も含まれます。ネタバレを避けたい方は、あらかじめご了承ください。
アート映画のカテゴリーにありながら、阿鼻叫喚のアクションと諧謔味に富んだ演出で観る者に強い印象を残した『ジャッリカットゥ 牛の怒り』(2019)。その監督リジョー・ジョーズ・ペッリシェーリの最新作『マライコッタイ・ヴァーリバン』がやってくる。特異な作家性の人リジョーと初めてコラボレーションするのは、マラヤーラム語映画界のスーパースターであるモーハンラール。近年はタミル語の『ジッラ 修羅のシマ』(2014)、『ジェイラー』(2023)、テルグ語の『ジャナタ・ガレージ』(2016)と、他言語作品での豪華な客演という形でしか日本で上映されてこなかったモーハンラールだが、その本拠地であるマラヤーラム語映画での主演作が久しぶりに日本の観客の目に触れることになる。
モーハンラールが演じるのは、“諸国漫遊ときどき道場破り”の旅をする豪放な武芸者ヴァーリバン。牛車で行動を共にするのは、彼が心から敬愛する師匠アイヤナールと、師匠の息子でヴァーリバンが弟分としてかわいがるチンナッパイヤン。チンナッパイヤンは、露払いとしてヴァーリバンの武勇を讃える口上を節をつけて触れ回ることもする。ヒーローが画面に登場する前から聞こえてくるこの口上がまず素晴らしい。南インド最古の文学であるサンガム期古タミル語韻文作品の中の長詩群は、放浪の旅芸人としての吟遊詩人により作詞され謡われたのではないかとする研究がある。チンナッパイヤンによる長々とした口上は、古代の吟遊詩人はこのように謡ったのではないかと思わせる魅力的なもので、物語が時空を超越したものであることを直感的に分からせてくれる。

実際に本作では、マラヤーラム語映画でありながらマラヤーラム語にタミル語が混じった言葉が話されている。また多くのエピソードが、緑豊かなケーララの風景とは異質な、乾ききって荒漠とした原野(ロケはかつて原爆実験が行われたこともある北インドのラージャスターン州ポークランで主に行われたという)で繰り広げられる。つまり本作は、いかなる時代、いかなる具体的な土地とも完全には符合しない、寓話的な無国籍風ファンタジー映画なのだ。無国籍映画は往々にして映像美を極める実験の場となり、物語は浅薄でペラペラなものとなりがちだが、モーハンラールの重厚と軽妙を織り交ぜた演技、A・V・ゴークルダースの美術とマドゥ・ニーラカンダンのカメラの巧みさにより、空疎に陥らず堅固な質感を持つ古譚の風格を保つ。
ヴァーリバンは、怪力・俊敏・狡獪さを兼ね備えた、負け知らずの超人的な剣士・格闘家。目的地があるようにも思えないその遍歴の旅は、絵巻物のように場所ごとに区切られて流れていき、同じようなエピソードが繰り返されながらも徐々に変化が加わり、それによりリズムが刻まれ、やがて大きな運命の渦が生まれる。そして間奏のように挟み込まれる荒野の移動や野営地のシーンで、主として独白によって注釈が加えられる。リジョー監督のトレードマークの一つである、水平線で上下に区切られたロングショットの画面も随所に効果的に現れる。そしてプラシャーント・ピッライの手になる、全盛期マカロニ・ウエスタンのエンニオ・モリコーネの音楽を明らかに意識したテーマチューンが、不敗戦士の孤愁を微かに暗示する。リジョー監督自身によれば、本作は日本のサムライ映画から大いに影響を受けており、またモーハンラールの言葉によれば、“映画的な禅”であるとのことだ。

風景が乾ききった褐色である一方で、そこに現れる人々やその営みはカラフルで変化に富んでいる。マラーティー語映画界出身のソーナーリー・クルカルニが演じる踊り子ランガラニがヌーラーナタラユールの町で披露するのは、マハーラーシュトラ州で民衆演劇と共に発展してきたラーヴァニーというダンスの雰囲気がうかがえる踊り。
ヴァーリバンがそこから武芸者としての遍歴をスタートさせた因縁の地であるアンバットゥール・マライコッタイでは、西欧人の王が恐怖政治を敷いている。当然ながらこのセグメントはイギリスをはじめとしたヨーロッパ列強によるインド植民地支配のメタファーであり、アクションシーンには、1919年に起きた大虐殺「ジャリヤーンワーラー・バーグ事件」を思わせる構図も出てくる。しかしアンドレア・ラヴェーラ(イタリア人)が演じる王とディアナ・ナソノヴァ(ロシア人)が演じる王妃は、マコーレーというアイルランド風の名前を持ちながら、イタリア語やロシア語、そしてたどたどしいマラヤーラム語を話すという自由さ。周りを固める兵たちは「プレジデンシー・アーミーズ」と称されたイギリス東インド会社の兵士のようであり、特徴的な真っ赤な制服を身にまとい、あたりに漂う赤い色粉と共に禍々しい殺戮の気配を漂わせる。王の周りではやし立てる白人の取り巻きたちは、まるで現代インドのビーチで寝そべるヒッピーのようだ(実際にビーチでリクルートされたエキストラなのかもしれない)。そしてヴァーリバンとの果し合いに臨むマコーレー夫妻の佇まいは、ほぼ格ゲーのそれである。


どす黒さを帯びた赤に染められたアンバットゥール・マライコッタイから、クライマックスのティルチェンドールの大平原に移ると、画面は一転して黄色に彩られる。とてつもない量の黄色いターメリック粉が大気中に舞うその情景は、まずマハーラーシュトラ州ジェージュリーのカンドーバー寺院で行われるバンダーラー(ターメリック)祭を思わせる。この奇祭はアーミル・カーン主演のヒンディー語作品『PK ピーケイ』(2014)のソング「Bhagwan Hai Kahan Re Tu〔神よ、どこにおわすのか〕」でも印象的に描かれていた。しかし本作中の「聖なる大馬祭」はそれだけではなく、ありとあらゆる要素が詰め込まれたカーニバルだ。巨大な張りぼての馬の行進はケーララ州中部のヴァダッカンチェーリで行われるマッチャード・マーマーンガム祭などで見られるもの。黄色く煙る熱気の中で踊る人々の中には、タミル地方の芸能であるクディライ(木偶の馬)を付けて踊っている者もいれば、カラガーッタムという舞踊のサブジャンルであるクラヴァン・クラッティ・アーッタムに特有のウルトラ・ミニスカートをはいた女性たちの姿もある。群衆のほとんどが仮面を着けているが、その仮面は必ずしも全てがインドのものではなさそうだ。仮面集団の中をさまようヴァーリバンの姿は、ベルギーの近代画家ジェームズ・アンソール(1860 - 1949)が描きつづけた仮面モチーフの絵画をも思い起こさせる。
『マライコッタイ・ヴァーリバン』は、リジョー監督の奔放な想像力が引き寄せた様々なイメージを万華鏡のように散りばめながら、しかし同時に不思議な静謐さも湛える類いまれな映画世界、浸り切るには劇場の大画面での没入がお勧めだ。
キャストほか
タイトル:マライコッタイ・ヴァーリバン
監督・脚本:リジョー・ジョーズ・ペッリシェーリ
撮影:マドゥ・ニーラカンダン
音楽:プラシャーント・ピッライ
出演:
マライコッタイ・ヴァーリバン:モーハンラール
ランガパッティナム・ランガラニ:ソーナーリー・クルカルニ
アイヤナール師父:ハリーシュ・ペーラディ
チャマタカン:ダーニシュ・セート
チンナッパイヤン:マノージ・モーゼス
ジャマンティ:コタ・ノンディ
2024年 / インド / 156分 / マラヤーラム語 / シネマスコープ / カラー / 5.1ch
原題:Malaikottai Vaaliban / 日本語字幕: 藤井美佳 / 字幕監修:粟屋利江 / 提供:JAIHO / 配給: グッチーズ・フリースクール
場面写真
















すでに登録済みの方は こちら